5月22日 晴れ
本日のBGM Billy Vaughn
人は2度死ぬ、1度目は体が死んだ時、2度目は誰からも忘れられた時、というのは有名な言葉ですが、似たような言葉で、人はフィルムに撮られると死ななくなる、というのも何処かで読んだような気がします。

今日福岡県で再放送された番組に庚申窯が出て、その中でまだ生きていた時の祖父が登場して、知っている方からは懐かしんでいただけたようですが、映像の中の元気な様子を見ていると 生きていた時の仕草や声など思い起こされて、ぼやけていた記憶の中の像が またはっきりと映し出されます。
故人の映像を見返すと、記憶の中の姿も そのたびに書き留められるし、それをきっかけに眠っていた記憶も呼び覚まされるから忘却という死がなくなるのでしょう。
また生前に会ったことがない人でも、生きている時の映像を見ると自分の中に実在の人として息づくから、映像に残っていると死なない、ということになるのだと思います。
そういう意味では現在の人たちはほとんど死ななくなっているのではないかしら。特にオンラインの世界に映像があれば、全てのサーバーが壊れない限りずっと映像が残り続けて、世代が変わっても再発見されて生き返ったりすることができそうですよね。

考えてみれば私が作業中によく聞く落語家なども全員死んでいるし、本日のBGMで紹介した人たちも半分くらい死んだ人たちで、そうすると私はいつも死んだ人間の声ばかり聞いてますが、その時は死んだことなど忘れてて、生きている人と同じように、その人たちは心の中で像を結んでいます。
歌声からは感情をもらって、言葉からはいろいろなことを学べますので、そうなってくると生きている人からの影響と、死んだ人からの影響というのは あまり差がないように思えます。十分に映像が残っている場合ですけどね。死後も作品が誰かに届いて、波及していくというのは作り手にとってはとても嬉しいことかもしれませんね。
なので祖父の作った品物も 生前と変わらず売っていて、もうだいぶ少なくなりましたが、なるべく庚申窯で保存しておこうとかはあまり考えていません。
というのも 器は資料として残し続けるより 誰かの役に立って割れていく方が正しい在り方だと思いますし、誰かが受け取ることで記憶が繋がれて、それが作り手を尊重する態度になると思うからです。
それといくらこの先 映像が残っていくとしても、それにもやはり寿命があると思います。例えば戦前の映画を好んで見る高校生は稀だと思いますし、器の形だって30年前くらいでもかなり今とは違っています。
だから祖父の作ったものもアップデートされなければ いずれ時代に合わなくなり、実用性がなくなって資料としての機能しかなくなると思うので、その前に器として用いられた方がいいと思います。
あの世や魂の世界というのは 人間がまだ解明できていない不思議なところ、とかではなくて、たぶんそれらは生きている人間の中に存在しているものだと 私は思います。
生きている人間という物質がなければ 形のない世界は存在できなくて、生きて思いや記憶をつなげていくことで、死んだ人間に寄り添うことができるのだと思います。
ところで死んだ人間は大体好感度が上がって、生前よりもいい人にされてしまいますが そんなに聖人君子だったかしら?嫌なところも笑って伝えておくこともまた死者への尊重になると思います。
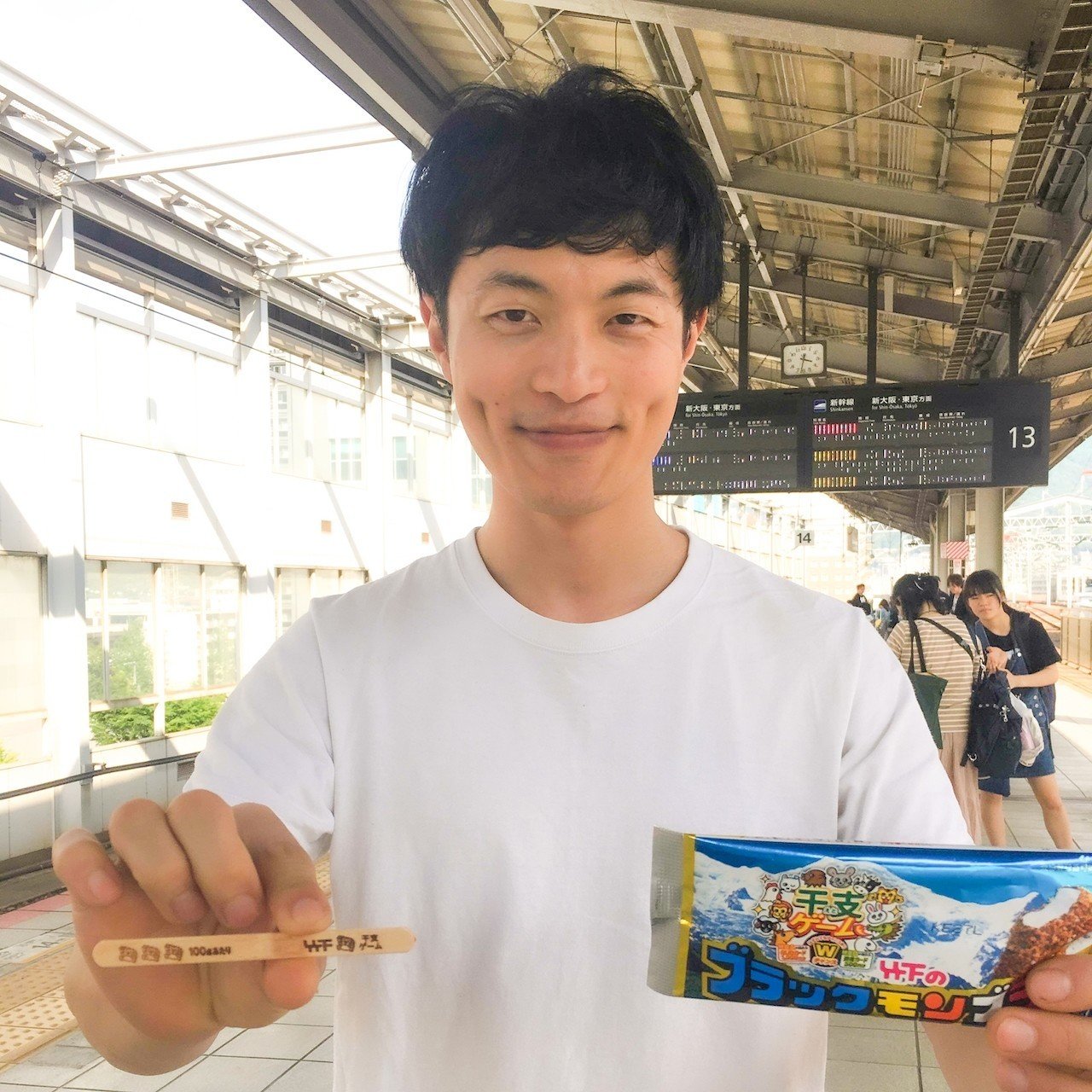
高鶴裕太 コウヅルユウタ
陶芸家
1991年生まれ
2013年横浜国立大学経済学部卒業
上野焼窯元 庚申窯3代目
